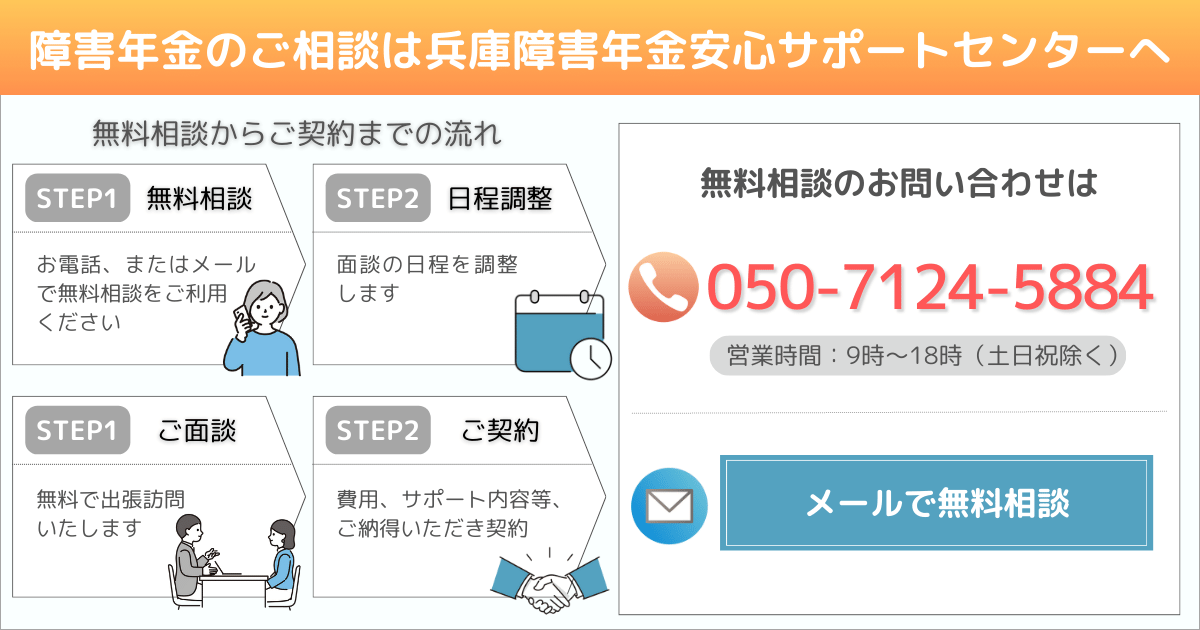「収入があると受給できないのでは?」と疑問に思う方も多いですが、実際には収入に影響されないケースがほとんどです。
本記事では、障害年金の基本的な受給条件から例外的な調整が必要なケース、さらに請求手続きのポイントまで詳しく解説します。働きながら生活を支えるために障害年金を賢く活用する方法を、わかりやすくお伝えします。
制度の仕組みを理解し、安心して働き続けられる環境を整えましょう!
障害年金は働いていても受給できるのか?
「障害年金は、働いていると受給できないのでは?」という疑問は多くの方が抱えるものです。特に、雇用保険や生活保護制度のように収入や資産が受給資格に影響すると考えがちですが、実際には違います。
厚生労働省の「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」によれば、障害基礎年金や障害厚生年金の受給者の約34%が就労しています。このデータには、障害福祉サービス事業所で働く人々も含まれていますが、受給者の3割以上が働きながら障害年金を受け取っているのが現状です。
そもそも、障害年金は収入制限が設けられている制度ではありません。保険料を支払った人が保険制度の恩恵として受け取れるものであり、現在の収入や資産の有無によって原則的に受給資格が失われることはありません。そのため、働きながら収入を得ても、障害年金の受給に影響することはないのです。
働きながら障害年金を受け取る条件と仕組み
障害年金は、働いているかどうかにかかわらず、一定の条件を満たしていれば受給できます。その基本条件は、障害の原因となった傷病の初診日や保険料納付状況、障害の程度によって判断されます。一方で、現在の収入や世帯収入は、原則として受給に影響しません。
たとえば、心臓ペースメーカーを装着している年収1000万円の会社員であっても、障害の状態が認定基準を満たしていれば障害年金を受け取ることが可能です。障害年金は、納めた保険料をもとに支給される仕組みであり、生活保護のような収入制限とは性質が異なるためです。
ただし、例外的に収入が受給額に影響するケースがあります。その一つが「20歳前障害基礎年金」です。この場合、初診日が20歳より前である場合に限り、所得制限が設けられています。年収が一定額を超えると、障害年金の支給額が減額または停止される可能性があるため、事前に確認が必要です。
障害年金は、仕事を続けながら安心して受け取ることができる制度です。条件を正しく理解し、受給資格を活用することで、生活の安定を図りながら働くことができます。
例外的な収入調整のケース
障害年金は原則として収入に影響されることなく受給できますが、例外的に収入や他の給付と調整が行われるケースがあります。ここでは、代表的な2つのケースについて解説します。
1. 20歳前障害基礎年金と収入の関係
20歳前に初診日がある障害基礎年金(20歳前障害基礎年金)は、所得制限の対象となる特別なケースです。この制度では、受給者の所得が一定の基準額を超えると年金額が減額されたり、場合によっては支給停止になる可能性があります。
所得制限
- 前年の所得が4,721,000円を超える場合、年金は全額支給停止。
- 前年の所得が3,704,000円を超える場合、年金の2分の1が支給停止。
扶養親族がいる場合の所得制限額の加算
- 扶養親族1人あたり38万円が所得制限額に加算されます。
- ※対象扶養親族が以下の場合、加算額が異なります:
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族:1人につき48万円を加算。
- 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満):1人につき63万円を加算。
支給停止期間
- 支給停止の適用期間は10月から翌年9月までの1年間。

2. 障害年金と傷病手当金の同時受給
障害年金と健康保険から支給される傷病手当金を同時に受け取る場合、同一の傷病が原因である場合に限り調整が行われます。同一傷病の場合、障害年金と傷病手当金の支給額が調整され、二重に受け取れない仕組みとなっています。ただし、以下のケースでは調整の対象外となります:
- 異なる傷病が原因の場合
- 障害基礎年金のみを受給している場合
この調整の仕組みを正しく理解することで、受け取れる金額や手続き上の注意点を把握しやすくなります。なお、障害年金を請求する際には、傷病手当金を受給中に手続きを進めるとスムーズに移行できるためおすすめです。
障害年金請求のタイミングと手続きのポイント
障害年金を受給するためには、正しいタイミングで手続きを進めることが重要です。請求のタイミングを逃すと受給開始が遅れる可能性があるため、早めの準備が鍵となります。ここでは、具体的なポイントを解説します。
1. 障害年金請求の最適なタイミング
障害年金の請求は、病気やけがによる障害が認定される状態になった時点で行います。ただし、請求には準備が必要な書類が多く、手続きには一定の時間がかかるため、障害の状態が続くと判断された時点で早めに着手することをおすすめします。
特に、傷病手当金を受給中の方は、障害年金への移行を視野に入れておくことが重要です。傷病手当金の受給期間が終了するまでに障害年金の受給が開始されるよう計画的に進めることで、収入の途切れを防ぐことができます。
2. スムーズな手続きのための準備
障害年金の請求には、以下のような書類の準備が必要です。
| 年金請求書 | 住所地のある市区町村役場、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にあり 障害基礎年金を請求する場合と障害厚生年金を請求する場合で様式が違う |
| 年金手帳など基礎年金番号がわかる書類 | 加入期間を確認するためのもの 提出できないときは、理由書が必要 |
| 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | 請求者の生年月日を確認するために必要 単身者でマイナンバー登録をしている場合、戸籍謄本等の添付が原則不要 年金請求書を共済組合等に提出する場合は、住民票等が必要になる場合も 障害年金の請求書類を提出する前1か月以内のものが有効 |
| 診断書 | 医師または歯科医師が作成したもの 所定の様式あり(8種類) 1.眼の障害用 2.聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声・言語機能の障害用 3.肢体の障害用 4.精神の障害用 5.呼吸器疾患の障害用 6.循環器疾患の障害用 7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 8.血液・造血器・その他の障害用 障害認定日より3か月以内に受診した時点の状態が書かれたもの(20歳に達した日が障害認定日(≒20歳前に初診日がある)の場合は「前後3か月」) 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内に受診した時点の状態が書かれたもの)も必要 呼吸器疾患の診断書を使用するときで、呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺含む)の疾病は、レントゲンフィルムの添付も必要 循環器疾患の診断書を使用するときで、心電図所見のあるものは、心電図のコピーの添付も必要 |
| 受診状況等証明書 | 障害の状態などを確認するための補足資料 パソコンで作成可(Excel様式が日本年金機構のホームページで公開中) |
| 病歴・就労状況等申立書 | 障害の状態などを確認するための補足資料 パソコンで作成可(Excel様式が日本年金機構のホームページで公開中) |
| 請求者名義の金融機関の通帳 | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分が含まれるもの 通帳でもキャッシュカードでも可(コピー可) 受給が決定すれば、この口座に障害年金が振り込まれる |
これらの書類を正確に準備し、申請先である年金事務所や市区町村の窓口で提出します。不備があると手続きが遅れる可能性があるため、社会保険労務士や年金相談センターに相談しながら進めると安心です。
3. 手続きの進捗を把握する方法
障害年金の審査期間は、通常スムーズに進めばおおよそ3か月ほどかかります。支給が決定した場合、日本年金機構から申請者宛に年金証書が郵送されます。
ただし、実際にはさまざまな事情で審査結果の通知が3か月以上経っても届かないケースも少なくありません。障害年金の申請後は、審査に数か月かかることが一般的です。進捗状況を確認するには、申請先の年金事務所に直接問い合わせるか、審査状況確認専用ダイヤル(03-5155-1933)を活用すると便利です。
電話がつながったらオペレーターに、以下の情報を伝えてください。
- 基礎年金番号
- 氏名
- 生年月日
- 住所
まとめ:障害年金を活用しながら、安心して働き続けるために
障害年金は、働きながらでも受給できる重要な支援制度です。多くの方が「収入があると受給できないのでは」と不安を抱えていますが、実際には多くのケースで収入制限の影響はありません。
この記事では、障害年金と就労の関係について具体的かつ分かりやすく解説しました。以下に重要なポイントをまとめます。
- 障害年金は原則、本人の収入や世帯収入に影響されない。
- 障害基礎年金の20歳前障害のみ、収入調整が行われる場合がある。
- 傷病手当金と障害年金は同時受給できるが、同一傷病の場合は調整が必要。
- 障害年金請求は傷病手当金受給中に進めるとスムーズに移行できる。
これらの知識を活用すれば、働きながら障害年金を賢く利用し、生活の安定を図ることができます。
疑問や不安がある方は、社会保険労務士や年金事務所に相談して正確な情報を確認してください。
障害年金を活用して、より安心して働き続ける環境を手に入れましょう。